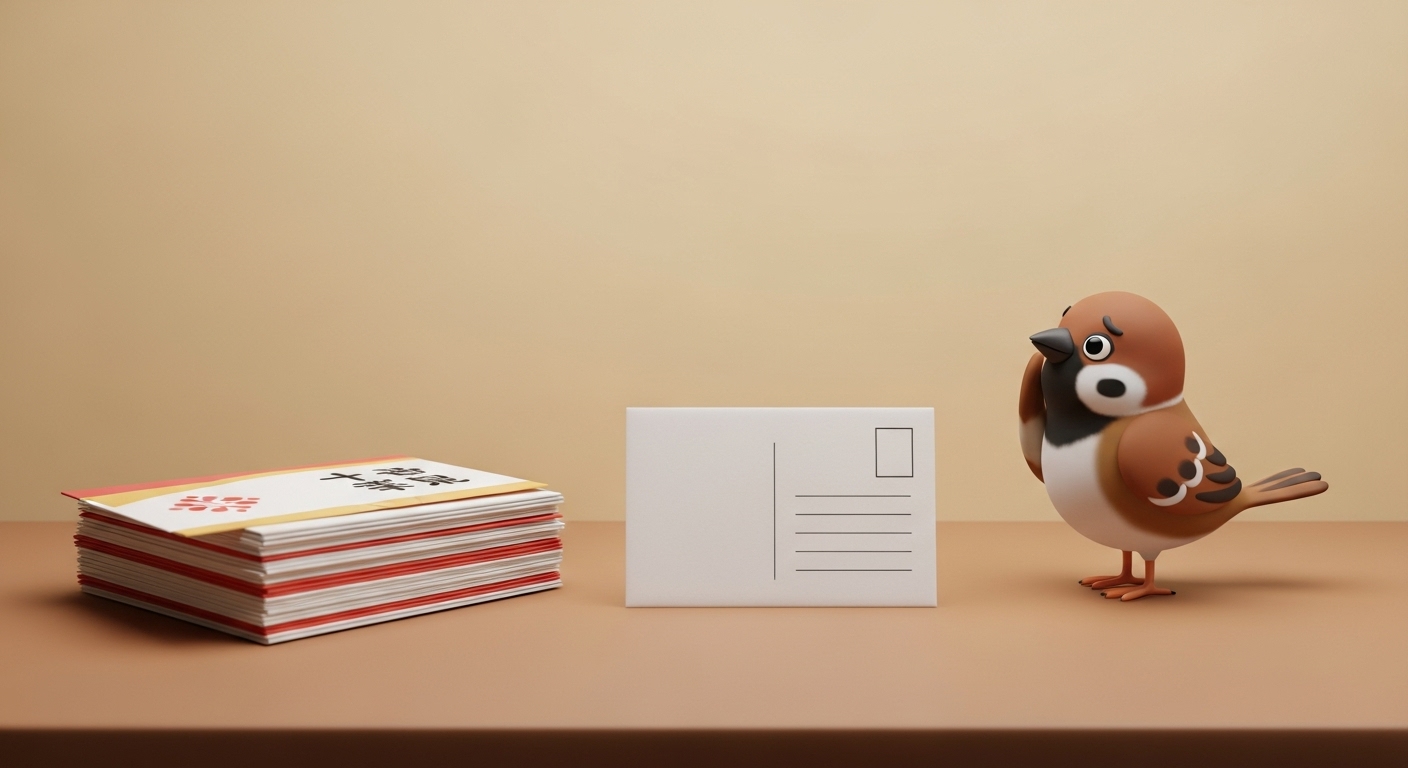「年末が近づいてきたけど、今年は喪中だから年賀状はどうしよう…」
「友人から喪中はがきが届いた。年賀状は出しちゃいけないの?」
毎年、新年のご挨拶としてお世話になっている年賀状。
でも、ご自身やお相手が喪中の場合、どう対応したらよいか迷ってしまいますよね。
マナー違反になってしまったらどうしよう、と不安に思うお気持ち、とてもよくわかります。
この記事では、年賀状と喪中のマナーについて、「自分が喪中の場合」「相手が喪中の場合」「うっかり間違えてしまった場合」の3つのパターン別にわかりやすく解説します。
- 喪中の基本的な意味と、年賀状を控える理由
- 【パターン別】自分が喪中・相手が喪中の時にすべきこと
- 喪中はがきや寒中見舞いの書き方・時期・文例
大切なのは、故人を偲び、相手を思いやる気持ちです。この記事を読んで、不安をスッキリ解消しましょう!
喪中ってどういうこと? 年賀状との関係(基本のキ)
(この見出しの要旨:喪中とは、近親者が亡くなってから一定期間、お祝い事を避けて静かに過ごす期間のこと。年賀状は新年を「お祝いする」挨拶状なので、喪中の方へ送ったり、喪中の方が送ったりするのは控えるのがマナーです。その理由と、基本的な範囲や期間をわかりやすく解説します。)
そもそも「喪中」とは? 期間はいつまで?
「喪中(もちゅう)」とは、ご家族や近しい親戚が亡くなった後、故人を偲(しの)び、身を慎んで過ごす期間のことを指します。
この期間は、お祝い事や派手な行動を避けて、静かに過ごすのが日本の伝統的な慣習です。
期間については厳密な決まりはありませんが、一般的には**亡くなってから1年間(一周忌法要まで)**を喪中とすることが多いです。
喪中になる「範囲」はどこまで?(二親等までが目安)
では、どの範囲の親族が亡くなると喪中になるのでしょうか。
これも明確な決まりはありませんが、一般的には**「二親等(にしんとう)」まで**が一つの目安とされています。
- 〇親等(自分から見て): 父母、配偶者(夫・妻)、子
- 一親等: 父母、配偶者(夫・妻)、子
- 二親等: 祖父母、兄弟姉妹、孫
ただし、二親等でなくても、生前に非常に親しくしていたご親族やご友人を亡くされた場合、ご本人の気持ちとして喪中とされることもあります。
なぜ喪中は年賀状を控えるの?(お祝い事だから)
年賀状は、新しい年を迎えたことを「お祝い」し、「おめでとうございます」という喜びの気持ちを伝える挨拶状です。
一方、喪中の方は、故人を偲び、静かに過ごす期間です。
そのため、お祝い事である年賀状のやり取りは控えるのがマナーとされています。
- 自分が喪中 → 新年を祝う気持ちになれないため、年賀状を出しません。
- 相手が喪中 → 相手は静かに過ごしているため、「おめでとう」という言葉を送るのを控えます。
「忌中」と「喪中」の違いは?
「忌中(きちゅう)」という言葉も聞いたことがあるかもしれません。
忌中も喪中と同じく、身を慎む期間ですが、意味合いや期間が少し異なります。
- 忌中: 故人が亡くなってから四十九日法要(神式では五十日祭)までの期間。特に身を慎むべき期間とされ、神社への参拝なども控えます。
- 喪中: 忌中を含む、約1年間の期間。
「忌中」が終わると、「忌明け(きあけ)」となり、少しずつ日常生活に戻っていきます。



喪中の範囲や期間は、あくまで「目安」です。地域の慣習やご家庭の考え方によっても変わってきます。一番大切なのは、故人を大切に思うお気持ちです。迷ったときは、ご家族や身近な方と相談してみるのが良いでしょう。
【パターン別】喪中と年賀状の対応マナー早分かり表
ご自身が今どの状況にあるか、下の表でチェックしてみてください。
やるべきことがすぐにわかりますよ。
| あなたの状況 | 年賀状は? | 代わりの挨拶は? |
| 自分が喪中 | 出さない | 喪中はがき(年賀欠礼状)を送る |
| 相手が喪中(喪中はがきを受け取った) | 出さない | 寒中見舞い(年明け)を送る |
| 相手が喪中(知らずに出してしまった) | – | すぐにお詫び+寒中見舞い |
| 自分が喪中(年賀状を受け取った) | – | 寒中見舞い(年明け)で返事 |
【自分が喪中の場合】年賀状はどうする?
(この見出しの要旨:ご自身が喪中の場合、年賀状は送らず、代わりに「喪中はがき(年賀欠礼状)」を送るのが一般的です。送る時期や相手、書き方の基本マナーと文例を解説します。)
年賀状は送らないのがマナーです
ご自身が喪中の場合、新年の「おめでとう」という挨拶は控えます。
そのため、年賀状は送らないのがマナーです。
毎年年賀状を交換している方々が「どうしたのかな?」と心配されないように、事前にお知らせをする必要があります。
「喪中はがき(年賀欠礼状)」を送りましょう
年賀状を送らない代わりに、「喪中はがき(年賀欠礼状)」を送ります。
これは、「喪中のため、新年のご挨拶(年賀状)を失礼させていただきます」ということを事前にお知らせするための挨拶状です。
喪中はがきはいつまでに出す?(11月〜12月上旬)
喪中はがきは、相手が年賀状の準備を始める前に届くように送るのがマナーです。
11月中旬から、遅くとも12月上旬までには相手に届くように手配しましょう。
もし間に合わなかった場合は、年が明けてから「寒中見舞い」としてご挨拶状を送ります。
喪中はがきは誰に出す?(毎年やり取りする人)
基本的には、「毎年年賀状のやり取りをしている人」全員に送ります。
ただし、故人が亡くなったことをすでに知っているご親族などには、送らなくても失礼にはあたらないとされています。
どこまで送るか迷った場合は、ご家族と相談して決めるとよいでしょう。
喪中はがきの基本的な書き方と文例
喪中はがきには、お祝い事を連想させる言葉(「賀」や「祝」など)や、派手なデザインは使いません。
切手も、弔事用のものか、落ち着いたデザインの普通切手を選びましょう。
【基本的な構成】
- 喪中であることのお詫び(年賀欠礼の挨拶)
- 誰がいつ亡くなったか(故人の氏名・続柄・没年齢・逝去日)
- これまでのお付き合いへの感謝
- 相手の健康を祈る言葉
- 日付
【文例】
喪中につき 年末年始のご挨拶を謹んでご遠慮申し上げます
本年〇月〇日に 〇〇(故人の続柄 例:父)〇〇(故人の氏名)が 〇〇歳にて永眠いたしました
これまで賜りましたご厚情に深く感謝いたしますとともに
明年も変わらぬご厚誼(こうぎ)のほどお願い申し上げます
時節柄 どうぞご自愛ください
令和〇年十二月
ビジネス(会社・取引先)関係の年賀状はどうする?
仕事関係の年賀状は、少し判断が分かれるところです。
- 個人の付き合いが強い場合: 喪中はがきを送るのが一般的です。
- 会社として出す(儀礼的な)年賀状: 喪中であっても、プライベートとは切り離して、会社名義で通常通り年賀状を送るケースも多いです。
迷った場合は、会社の上司や総務部門に相談してみましょう。
喪中でも年賀状を受け取りたい・送りたい時は?
「喪中だけど、親しい友人からの年賀状は受け取りたい」
「お祝いの言葉は使わずに、新年の挨拶だけ送りたい」
というお気持ちになることもあるかもしれません。
しかし、年賀状は「お祝い」の意味合いが強いため、喪中に送ったり、受け取りを希望したりすることは、基本的には避けるのが無難です。
大切なご友人には、年明けに「寒中見舞い」を送って、近況を伝え合うのがおすすめです。



喪中はがきを出すのは、少し気が重いかもしれませんね。でもこれは、相手に「年賀状を送らないでください」と伝えるためではなく、「心配をかけないように、事前にお知らせします」という思いやりの挨拶状なんです。
【相手が喪中の場合】年賀状はどうする?
喪中はがきを受け取ったら年賀状は送らない
お相手から喪中はがきが届いたら、その方への年賀状は送らないようにしましょう。
「おめでとうございます」というお祝いの言葉は、悲しみの中にある方にとってはつらいものになってしまうかもしれません。
もし、すでに年賀状を投函してしまった後に喪中はがきが届いた場合は、次の「うっかり!」の章を参考にしてください。
年賀状の代わりに「寒中見舞い」を送りましょう
年賀状は送りませんが、かわりに「寒中見舞い(かんちゅうみまい)」を送ることで、お悔やみや励ましの気持ちを伝えることができます。
寒中見舞いは、寒さが厳しい時期に相手の健康を気遣う挨拶状です。
寒中見舞いはいつ送る?(松の内が明けてから)
寒中見舞いを送る時期にはマナーがあります。
年賀状のやり取りをする期間である「松の内(まつのうち)」が明けてから送ります。
- 松の内: 1月1日〜1月7日(または1月15日 ※地域による)
- 寒中見舞いの時期: 松の内が明けてから〜立春(りっしゅん:2月4日頃)まで
年が明けて、少し落ち着いた頃(1月7日以降)に届くように送りましょう。
寒中見舞いの書き方と文例(お悔やみを添えて)
寒中見舞いも、お祝いの言葉は使いません。
年賀はがきではなく、通常のはがきや落ち着いたデザインのはがきを使います。
【基本的な構成】
- 寒中見舞いの挨拶
- (喪中はがきへの返礼の場合)お悔やみの言葉、ご家族を気遣う言葉
- 近況報告(省略してもOK)
- 相手の健康を祈る言葉
- 日付
【文例(喪中はがきを受け取った場合)】
寒中お見舞い申し上げます
この度は ご服喪(ごふくそう)中と伺い
年頭のご挨拶は控えさせていただきました
〇〇(故人の続柄 例:お父様)のご逝去を心よりお悔やみ申し上げます
ご家族の皆様は さぞかしご傷心のこととお察しいたします
寒い日が続きますので どうぞご無理なさらないようご自愛ください
令和〇年一月
年始の挨拶(メールやLINE)はどうする?
喪中の方に対して、メールやLINEで「あけましておめでとう」と送るのは、年賀状と同じく避けた方がよいでしょう。
もし連絡を取りたい場合は、年明け(松の内が明けてから)に、
「寒い日が続きますが、お変わりないですか?」
「体調など崩されていませんか?」
といった、相手を気遣う内容を送るのが思いやりです。



喪中はがきを受け取ったら、「返事を書かなくちゃ」と焦る必要はありません。まずは年賀状を送らないように気をつけて、年が明けてから「寒中見舞い」で、ゆっくりと言葉を選んでお悔やみを伝えましょう。
【うっかり!】喪中と知らずに年賀状を出した/受け取った時の対処法
喪中であることを知らずに、年賀状をやり取りしてしまうこともありますよね。
そんな時も、慌てなくて大丈夫です。誠意をもって対応すれば、お相手にも気持ちは伝わります。
1. 相手の喪中を知らずに年賀状を出してしまった場合
年賀状を出した後に、お相手が喪中だったことを知った(喪中はがきが届いた、人から聞いたなど)場合の対応です。
すぐに電話や手紙でお詫びを伝える(文例あり)
まずは、気づいた時点ですぐにお詫びの連絡を入れましょう。
電話が確実ですが、難しい場合は手紙(お詫び状)や、ごく親しい間柄ならメールなどで、失礼をお詫びします。
【お詫びの言葉(電話の場合)】
「〇〇様(故人)が亡くなられたこととは存じ上げず、年賀状をお送りしてしまい、大変失礼いたしました。心よりお悔やみ申し上げます。」
あらためて寒中見舞いを送る
お詫びの連絡とは別に、年明けの「松の内」が明けてから、あらためて「寒中見舞い」としてお悔やみの挨拶状を送りましょう。
この際、お詫びの言葉を添えるとより丁寧です。
【文例(寒中見舞いにお詫びを添える場合)】
寒中お見舞い申し上げます
この度は 〇〇様(故人)のご逝去を存じ上げず
年賀状をお送りしてしまい 大変失礼いたしました
遅ればせながら 謹んでお悔やみ申し上げますとともに
ご家族皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます
令和〇年一月
2. 自分が喪中なのに年賀状を受け取ってしまった場合
ご自身が喪中の時に、年賀状が届くこともあります。
これは、喪中はがきが何らかの事情で届かなかったか、出すのが間に合わなかった場合がほとんどです。
お相手は喪中を知らなかっただけ。気にしなくて大丈夫
年賀状を送ってくださった方は、あなたが喪中であることを知らなかっただけです。
悪気があって送ったわけでは決してないので、お相手を責めたり、気に病んだりする必要はありません。
年明けに「寒中見舞い」で返事をしましょう(文例あり)
年賀状をいただいたお礼と、喪中であったことをお伝えするために、年明けの「松の内」が明けてから「寒中見舞い」として返事を送りましょう。
【文例(喪中に年賀状を受け取った場合の返事)】
寒中お見舞い申し上げます
ご丁寧な年賀状をいただき ありがとうございました
昨年〇月に〇〇(故人)が他界いたしましたため
年末年始のご挨拶を失礼させていただきました
ご連絡が行き届かず 申し訳ございません
寒い日が続きますが どうぞご自愛ください
令和〇年一月



「うっかり」は誰にでもあります。特に年賀状は、年末の忙しい時期に準備しますからね。もし間違えてしまっても、落ち込まないでください。大切なのは、その後の誠実な対応です。
喪中の年賀状に関するよくある質問(FAQ)
喪中の年賀状に関して、特に疑問に思いやすい点をQ&A形式でまとめました。判断に迷ったときの参考にしてください。
Q. 喪中の範囲は兄弟や祖父母だとどうなりますか?
A. 兄弟や祖父母は「二親等」にあたるため、一般的には喪中となります。
ただし、同居しているかどうか、生前の関係性の深さなどによっても変わってきます。
例えば、ご結婚されて世帯が別になっている兄弟や、交流が少なかった祖父母の場合、喪中としないケースもあります。
最終的にはご家族の判断や、ご自身のお気持ちで決めていただくのがよいでしょう。
Q. 喪中はがきをもらったら返事は必要ですか? メールでもいい?
A. 喪中はがき(年賀欠礼状)は、「年賀状を欠礼します」というお知らせなので、基本的にお返事は必要ありません。
もし、お悔やみの気持ちを伝えたい場合は、年が明けて「松の内」が過ぎてから、「寒中見舞い」を送るのが丁寧なマナーです。
ごく親しい間柄であれば、メールやLINEで「おはがきありがとう。大変だったね。無理しないでね」と、お相手を気遣うメッセージを送ってもよいでしょう。
Q. 喪中に年賀状の代わりにLINEやメールで新年の挨拶はしてもいいですか?
A. 「あけましておめでとうございます」というお祝いの言葉は、LINEやメールであっても控えるのがマナーです。
もし年始に挨拶を送りたい場合は、松の内(1月7日頃まで)が明けてから、
「ご挨拶が遅れましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします」
「寒い日が続きますが、お変わりなくお過ごしでしょうか」
といった、お祝いの言葉を避けた内容で送るようにしましょう。
Q. 会社の上司や同僚が喪中の場合、年賀状はどうすればいいですか?
A. 会社関係の方(上司、同僚、取引先)が喪中であると知っている場合は、個人名での年賀状は送らないのがマナーです。
相手が喪中であることを知らない他の同僚が年賀状を出してしまう可能性もあるため、可能であれば部署内などで情報を共有しておくと親切です。
年賀状の代わりに、年明けに寒中見舞いを送ったり、仕事始めの際にお悔やみの言葉を直接お伝えしたりするとよいでしょう。
Q. 喪中にいただいたお香典のお返しと、年賀状(寒中見舞い)は別ですか?
A. はい、別物です。
お香典のお返し(香典返し)は、四十九日法要が終わった「忌明け」のタイミングでお送りするのが一般的です。
一方、年賀状の代わりのご挨拶(喪中はがきや寒中見舞い)は、年末年始のご挨拶に関するものです。
時期も目的も異なるため、それぞれ別に対応するのがマナーです。
まとめ:喪中の年賀状はマナーと思いやりで対応しましょう
喪中の時の年賀状マナーについて、パターン別にご紹介しました。
押さえておきたいポイント
- 喪中は「お祝い事」を控える期間。年賀状もその一つです。
- 自分が喪中 → 年賀状は出さず、「喪中はがき」を12月上旬までに送る。
- 相手が喪中 → 年賀状は出さず、年明けに「寒中見舞い」を送る。
- うっかり間違えた → すぐにお詫びし、寒中見舞いで改めてご挨拶する。
いろいろな決まり事があって難しく感じるかもしれませんが、根底にあるのは「故人を静かに偲びたい」という気持ちと、「相手を気遣う」という思いやりの心です。
マナーの形も大切ですが、一番はあなたの温かい気持ちです。
この記事が、あなたの不安を解消するお手伝いになれば幸いです。